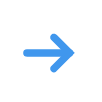化粧品に含まれている「pH調整剤」がどんなものかご存じですか。
結論から言うと、pH調整剤は製品の品質を安定させる重要な成分です。
本記事では、pH調整剤の基礎知識や選び方について詳しく解説します。
最後まで読めば、pH調整剤を上手く活用するポイントが分かり、消費者から信頼される商品づくりのヒントが得られるはずです。
\pH調整剤にも精通するOEM!/
資料をダウンロードする▶pH調整剤とは|製品の品質と肌へのやさしさを両立させる成分
pH調整剤は、化粧品のpH(酸性やアルカリ性の度合い)を適切に保つために配合される成分です。化粧品が肌にしみたり刺激を与えたりしないように、使いやすい状態に保つために使われます。
以下で、皮膚との関係性やpH調整剤活用のリスクについて解説します。
- pHと皮膚の関係
- pH調整剤の安全性とリスク
pHと皮膚の関係

人の肌は外部刺激や細菌から守るために、pH4.5〜6.0の弱酸性に保たれています。この弱酸性状態がバリアの役割を果たし、肌の乾燥や炎症を防ぎ、健康な状態を維持しているのです。
化粧品のpHが4.5~6.0から外れると、肌が刺激を受けやすくなり、かゆみや乾燥などのトラブルを引き起こす可能性があります。
化粧品を開発する際は、製品のpHを測定し、肌にやさしい弱酸性に調整しましょう。敏感肌や乾燥肌の方でも使いやすい製品設計が実現できます。
pH調整剤の安全性とリスク
化粧品に使われるpH調整剤は、製品の品質と肌へのやさしさを両立するのに必要な成分です。
pH調整剤にはクエン酸やアスコルビン酸などがあり、比較的安全性が高いとされています。
一方で、水酸化ナトリウムやトリエタノールアミンなどは、高濃度で使用すると皮膚刺激やアレルギー反応を起こす可能性があるため、配合量の管理が重要です。
実際の化粧品では、いずれの成分も適切な濃度で配合されており、通常の使用なら大きなリスクはありません。
開発の際は、成分ごとの安全性データを確認し、パッチテストなどを徹底しましょう。
pH調整剤が化粧品に必要な理由4選
pH調整剤が化粧品に必要な理由は、以下の4つです。
- 化粧品の安定性を高める
- 有効成分の効果を高める
- 微生物汚染を防止する
- 官能特性を保つ
なぜpH調整剤を配合すべきかを把握しておけば、処方設計時に製品の安定性や安全性を高めやすくなります。
pH調整剤を適切に活用すれば、肌トラブルや品質クレームのリスクを減らせるでしょう。
化粧品の安定性を高める
pH調整剤は、化粧品の成分の分解や変色、分離を防ぐために使われます。
例えば、乳液やクリームはpHが適切でないと、油分と水分が分離しやすくなり、見た目や使い心地が低下します。
pH調整剤を使って製品のpHを一定に保てば、長期間安定した状態の維持が可能です。製造時は、pHメーターなどでpH値をこまめに測定し、基準値に合わせて調整しましょう。
安定性の高い化粧品は、流通や保管中の品質トラブルを減らし、ブランドの信頼向上につながります。
有効成分の効果を高める
化粧品に含まれる有効成分は、pH環境によって効果が大きく変化します。
例えば、ビタミンC誘導体やグリコール酸などのAHAは、特定のpH範囲で最大の効果を発揮する成分です。
pH調整剤の活用で成分が分解しにくくなり、安定して肌に作用します。
製品の機能性と差別化を実現するには、ターゲットとする効果や成分の特性を把握し、最適なpH環境を維持する設計が必要です。
微生物汚染を防止する
化粧品は水分や有機成分を多く含むので、放置すると細菌やカビが繁殖しやすくなります。
pH調整剤を使って、製品のpHを4.5〜6.0の弱酸性に保てば、微生物が増えにくい環境をつくれます。
pH調整剤と防腐剤の併用で衛生的な製品設計を行い、製造時にはpH測定を徹底しましょう。
流通や使用中の品質トラブルを未然に防ぎ、消費者に安心して使ってもらえる化粧品を提供できます。
官能特性を保つ
官能特性とは、色や香りといった五感で感じられる特性のことです。pH調整剤は、化粧品の官能特性を安定させる重要な役割を果たします。
例えば、pH4.5〜6.0の範囲から外れていると、ローションが白く濁ったり、クリームが分離してしまったり、香りが変わったりする可能性があります。
官能特性の変化は、消費者の使用感や見た目の印象を大きく損なう原因です。製品のpHを一定に保てば、見た目の美しさやなめらかなテクスチャー、心地よい香りを維持しやすくなります。
pH調整剤の種類3選
pH調整剤の種類は、大きく分けて以下の3つです。
- 酸性pH調整剤
- アルカリ性pH調整剤
- 緩衝剤・その他の成分
それぞれ特徴や用途が異なるため、違いを理解しておけば処方設計の際に役立つはずです。
酸性pH調整剤
酸性pH調整剤は、肌への刺激を抑えて製品を弱酸性に保ち、安定性や使用感を向上させます。酢酸やリンゴ酸などの有機酸も、pH調整や保存性向上に活用される成分です。
化粧品に使われる酸性pH調整剤には、以下のような種類があります。
| 種類 | 主な特徴・用途 |
| クエン酸 | 柑橘類や梅などに含まれる有機酸。pHを下げたり、角質をやわらかく整えたりする働きがある。 |
| 乳酸 | 発酵由来の成分。保湿をサポートしながら、穏やかなピーリング作用も期待でき、肌をなめらかに整える目的でも使われる。 |
| グリコール酸 | AHAの一種。古い角質をやさしく取り除きながらpHを調整する。 |
| アスコルビン酸 | ビタミンCとして知られ、抗酸化ケアや製品のpH調整に利用される。 |
| 有機酸各種 | リンゴ酸や酢酸など、さまざまな有機酸があり、pH調整や製品の安定性維持に役立つ。 |
pH調整剤の選定は、製品の目的やターゲットに合わせて慎重に行いましょう。
アルカリ性pH調整剤
主にアルカリ性pH調整剤は、製品をアルカリ性に調整したい場合や乳化の安定化、成分の溶解性向上に利用します。
化粧品に使われるアルカリ性pH調整剤の例として、以下のようなものがあります。
| 種類 | 主な特徴・用途 |
| 水酸化ナトリウム | 強アルカリ性で石けんやクレンジング製品のpH調整に使用する。配合量や使用方法には注意が必要。 |
| 水酸化カリウム | 強アルカリ性。増粘剤と組み合わせて乳化の安定性を高める目的で使われる。高濃度では刺激になる可能性がある。 |
| アルギニン | アミノ酸の一種。マイルドなアルカリ性で、肌への刺激が少ない。 |
| トリエタノールアミン | 弱アルカリ性で乳化剤やpH調整剤として使用する。配合量に注意が必要。 |
| トロメタミン | 弱アルカリ性。安定した処方づくりに役立つ。 |
製品開発の際は、各成分の特性や肌への刺激性を理解し、適切な配合量を守ったうえで安全性試験を行いましょう。
緩衝剤・その他の成分
pHを一定に保つ目的で化粧品に配合されるのが、緩衝剤です。
例えば、以下のような化粧品に配合される緩衝剤やその他のpHを調整する成分があります。
| 種類 | 主な特徴・用途 |
| クエン酸ナトリウム | 金属イオンによる沈殿や酸化を防ぎ、化粧品の安定性を高める。 |
| リン酸塩類 | 多くのスキンケアやヘアケア製品で安定化目的に使われる。 |
クエン酸ナトリウムやリン酸塩類などのpH調整剤を適切に選べば、製品の品質維持や肌へのやさしさを両立できるので、積極的に活用すべき重要な成分です。
pH調整剤の選び方3選
pH調整剤の選び方は、以下の3つです。
- 製品の目的やターゲットに合わせる
- 成分の安全性と刺激性を確認する
- 製品の安定性や他成分との相性を考慮する
一口にpH調整剤と言っても、さまざまな種類や用途があるので、目的に合わせた選定が重要です。処方設計の際に参考にしてみてください。
製品の目的やターゲットに合わせる
pH調整剤を選ぶ際は、化粧品の用途やターゲットに合わせましょう。
例えば、敏感肌向けのスキンケア製品では、クエン酸や乳酸など刺激の少ない弱酸性のpH調整剤を使い、肌への負担を最小限に抑えます。
一方、洗顔料やクレンジングなど洗浄力を重視する製品では、汚れがしっかり落ちるよう、ややアルカリ性の処方に調整します。
ターゲットユーザーの具体的なニーズをリサーチし、ベストなpH調整剤を選定すれば、差別化や市場での競争力強化につながるはずです。
自社のターゲットと相性のよい成分が分からない場合は、化粧品OEMメーカーへの相談がおすすめです。
成分の安全性と刺激性を確認する
pH調整剤にはさまざまな種類があり、成分によっては肌への刺激やアレルギーを引き起こすリスクがあります。
例えば、水酸化ナトリウムやトリエタノールアミンは、高濃度で配合すると皮膚刺激やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。各成分の安全性データや配合基準を確認し、必要に応じてパッチテストや安全性試験を実施しましょう。
また、全成分表示やアレルギーリスクに関する注意事項を、パッケージや公式サイトで明確に伝えておけば、消費者の信頼を得やすくなります。安全性への徹底した配慮は、ブランドイメージの向上やリピート購入にもつながります。
製品の安定性や他成分との相性を考慮する
pH調整剤は、化粧品の保存料や有効成分と化学反応を起こす可能性があり、製品の安定性や品質に大きく影響します。
例えば、ビタミンC誘導体は強アルカリ性のpH調整剤と一緒に配合すると、分解しやすく効果が低下する場合があります。
また、保存料の防腐効果もpHによって変わるため、適切な組み合わせが必要です。
OEMメーカーや専門家と連携し、試作段階で各成分との相性テストや安定性試験を実施しましょう。成分同士の相性を考慮すれば、長期間安定した高品質な化粧品の開発が実現します。
pH調整剤を配合したアイテム例3選
pH調整剤を配合したアイテムの例を3つ紹介します。
- アスタリフト「ホワイト アドバンスドローション」
- ライスフォース「 ディープモイスチュアクリーム」
- キュレル「潤浸保湿 泡洗顔料」
アスタリフト「ホワイト アドバンスドローション」
引用:アスタリフト公式サイト
| 商品名 | ホワイト アドバンスドローション |
| 区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 130mL |
| 価格 | 4,180円(税込) |
| 特徴 | ・ナノマルチショット成分(*1)で乾燥によるくすみにアプローチする。 ・美白有効成分トラネキサム酸と抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。 |
アスタリフトの「ホワイト アドバンスドローション」は、ナノテクノロジーを活用した医薬部外品の美白化粧水です。
美白有効成分のトラネキサム酸と、抗炎症成分のグリチルリチン酸ジカリウムを配合し、メラニンの生成を抑えてシミやそばかす、肌荒れを防ぎます。
ナノ化したアスタキサンチンや3種類のコラーゲンなどの保湿成分をバランスよく配合。
pH調整剤により、成分の安定性と肌へのやさしさを両立しており、みずみずしいテクスチャーで使いやすい製品です。
(*1)ブライト保湿成分:ツボクサエキス、フェルラ酸、ビルベリー葉エキス、ユキノシタエキス。ブライトとは、うるおいによる透明感。
ライスフォース「 ディープモイスチュアクリーム」
引用:ライスフォース公式サイト
| 商品名 | ディープモイスチュアクリーム |
| 区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 30g |
| 価格 | 8,800円(税込) |
| 特徴 | ・ライスパワーNo.11エキス(*2)配合で皮膚水分保持能を改善する。 ・しっとりした使用感で長時間肌のうるおいを保つ。 |
ライスフォースの「ディープモイスチュアクリーム」は、ライスパワーNo.11エキスを主成分とし、高い保湿力がある薬用保湿クリームです。
クエン酸やクエン酸NaなどのpH調整剤を活用し、クリーム全体を弱酸性に保つことで、保湿成分の品質を安定させています。肌をすこやかに保ち、なめらかなテクスチャーと長時間続くうるおい感を実現しています。
敏感肌や乾燥肌の方にも使いやすい低刺激設計が特徴で、日々のスキンケアに最適なクリームです。
(*2)国産米100%を原料とし、独自の発酵技術「日本型バイオ」によってつくり出した肌をうるおす成分
キュレル「潤浸保湿 泡洗顔料」
引用:花王公式オンラインストア
| 商品名 | 潤浸保湿 泡洗顔料 |
| 区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 150mL |
| 価格 | 1,760円(税込) |
| 特徴 | ・弱酸性・無香料で敏感肌にもやさしい泡タイプ。 ・セラミド機能成分(*3)配合で洗い上がりのうるおいを守る。 |
キュレルの「潤浸保湿 泡洗顔料」は、敏感肌向けに開発された泡タイプの洗顔料です。クエン酸やクエン酸NaなどのpH調整剤を配合しており、洗顔時も肌にやさしい弱酸性を維持します。
セラミドケア成分や保湿成分の安定性を高めることで、洗い上がりのつっぱり感を抑え、しっとりとした肌を保ちます。
毎日の洗顔でうるおいを保ちながら、清潔ですこやかな肌状態をサポートする処方です。
(*3)ラウロイルアスパラギン酸Na液、ヤシ油脂肪酸アシルグルタミン酸Na
まとめ|pH調整剤を配合した製品開発ならベイコスメティックス
pH調整剤は、化粧品の品質維持と肌へのやさしさを両立してくれる成分です。pH調整剤について正しく理解し、適切に活用すれば、競争力のある高品質な商品開発が実現できるでしょう。
「ベイコスメティックス」では、成分の種類や相性について知見のある担当者が、企業様の商品開発を徹底サポートします。
処方設計から販路開拓まで一貫して支援するため、成分などの知識がない企業様も安心してお任せいただけます。
気になった方は、以下から無料の資料をダウンロードして、詳しい内容を確認してみてください。
\pH調整剤にも精通するOEM!/
資料をダウンロードする▶
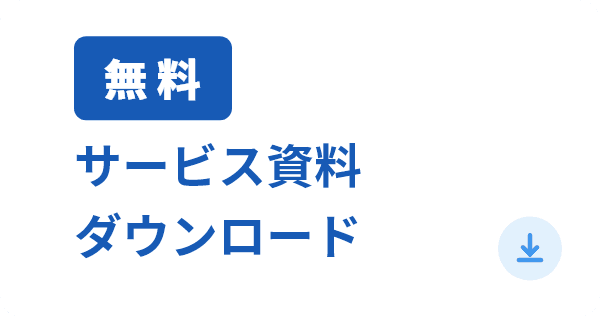





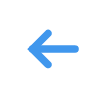 前の記事へ
前の記事へ