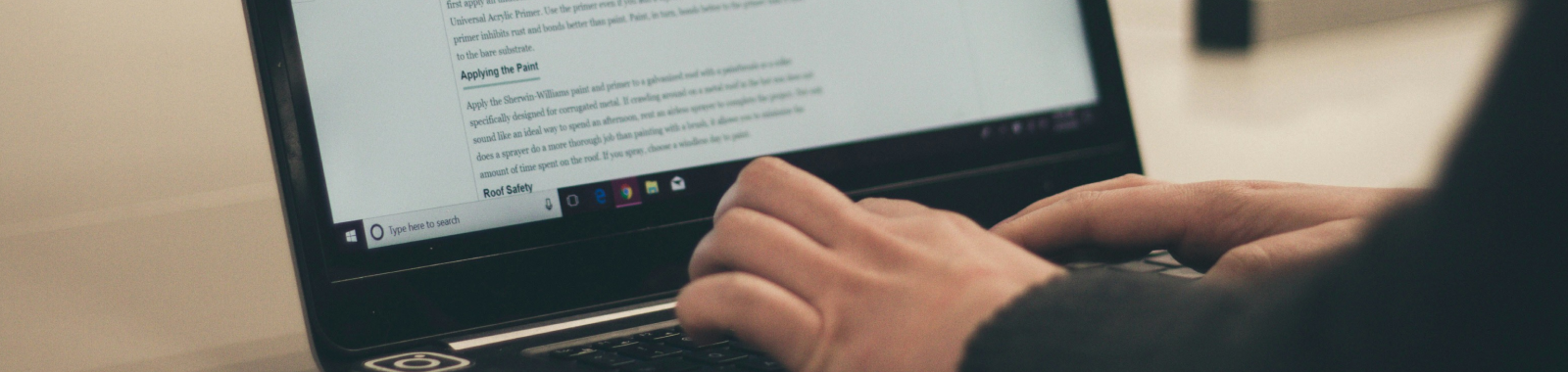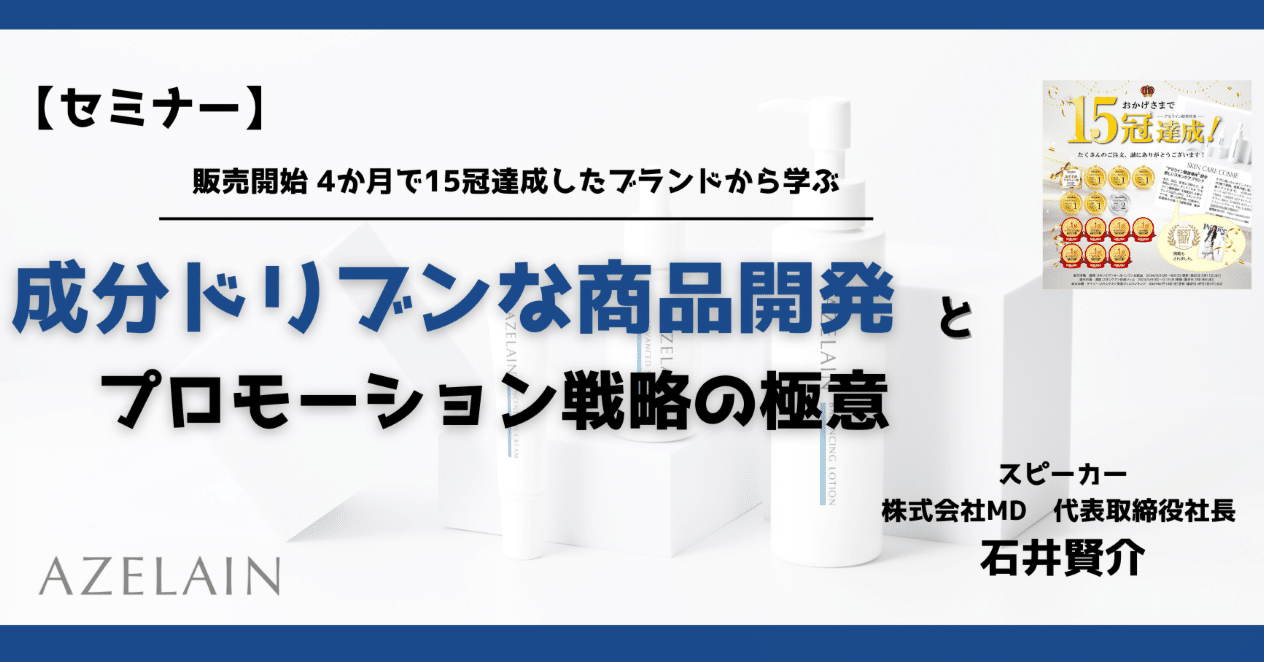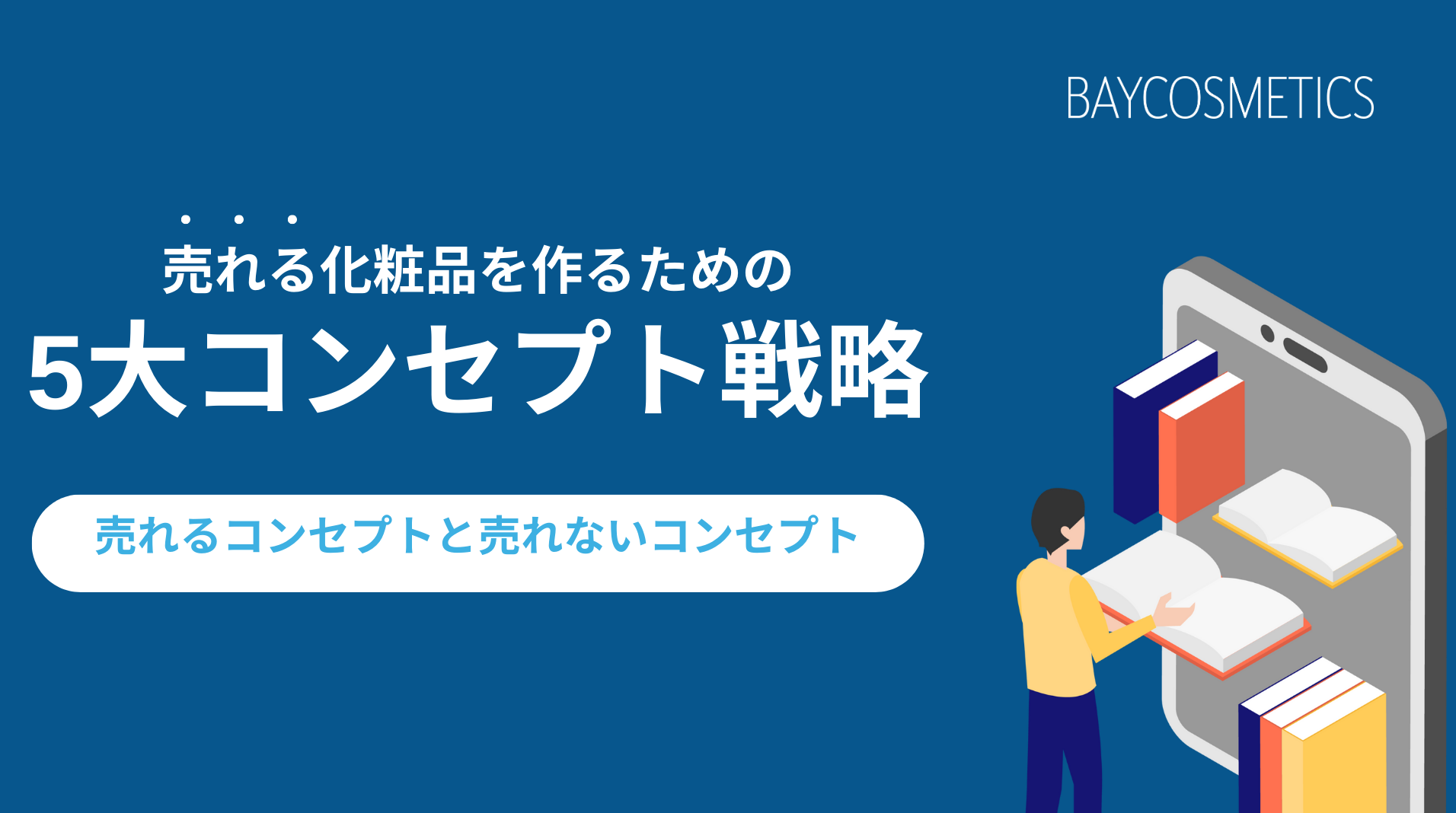質問:「売れる成分とは?」
回答:1.お金をかけて成分そのものの認知が自分たちで作れるもの 2.検索ボリュームが大きいもの
質問:「成分ドリブンで作った商品のプロモーション戦略は?」
回答:その成分にどんな効果・効能が期待できるのか、その成分がどれくらい入っているのかを訴求していく
質問:「D2C向け、モール向け、オフライン向けの成分に違いはありますか?」
回答:新しいものでチャレンジしたいならD2C、メジャーな成分ならモール、オフラインならどっちでもいける可能性がある選んでもらうことが難しい場合も
質問:「今、注目している成分は?」
回答:美容医療の領域からの転用は今後も増えていく、具体的にはPDRNやBHAなど
質問:「最近は、化粧品を専属としない他業界からの参入が多いと聞きますが、どういった業界からの参入が多いですか?」
回答:広告マーケティング業界は多い気がする
質問:「投資効果のイメージをご教示いただきたいです」
回答:発売して1年で利益率20%を目標
質問:「商品開発、成分広告、商品広告にかける費用の割合を教えてください」
回答:ビジネスによりけり、D2Cや大手企業などで異なる
成分ドリブンな化粧品開発・OEMならBAYCOSMETICSに相談!
\“売れる”まで サポートする化粧品OEM!/
資料をダウンロードする▶一問一答式で石井より回答させていただきましたが、多くのクライアント企業様や、お問い合わせの際にご質問いただく内容でしたのでアーカイブを記事化させていただきました。
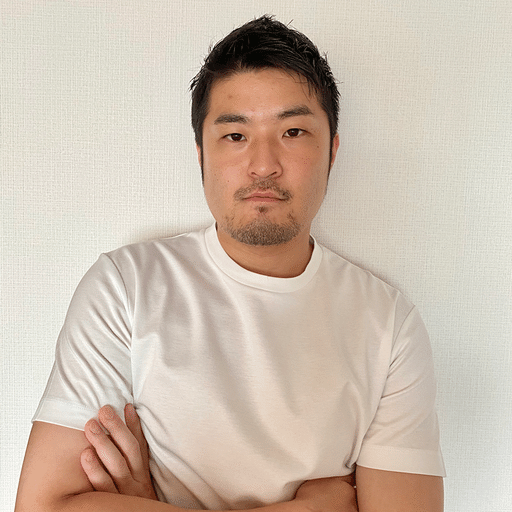
登壇者:石井賢介/株式会社MD代表取締役社長 1990年生まれ。東京大学農学部卒業。住友商事、P&Gを経て、主にマーケティング支援事業をおこなう『株式会社MD』を創業。200社以上の企業を支援。さらに昨今は、自社でも食品や化粧品のブランドを展開すべく、『株式会社ベイコスメティックス』を設立。マーケティングを軸とした商品・処方開発からチャネル支援にいたるまでの幅広いディレクションを実施している。
前編は”成分ドリブン”のトレンドの背景などについてお話させていただきました。前編の内容は以下よりご覧ください!
https://baycosme.com/seminar-archive-component-driven-2
後編では、トレンドの成分、売れる成分など、どのように”成分ドリブン”を取り入れていくかについて一問一答の形でお話していければと思います。
Q4「売れる成分とは?」
石井:今現在売れている成分を調べるのは簡単です。AmazonでもGoogleでも、各成分がどれくらい検索されているのかは一発で調べることができます。Amazonで基本的に一番多く検索されているのはビタミンCで、ちょっと前まではレチノールでした。直近ではアゼライン酸、時点がグルタチオンといった感じです。
じゃあ「どんな要素があれば売れるんだろう?」と考えると、1つには、“有名であること”が挙げられると思います。ビタミンCにしてもレチノールにしても、美容分野においてそこそこ知名度がある。
それに対して、アゼライン酸やグルタチオンは、医療だとかの他のカテゴリーで知名度があったものの、当初はアーリーアダプターが使っていた程度ですよね。ヒト幹細胞、エクソソームなんかもそう。“なんだかわからないけどすごそう”というイメージの人がほとんどなんじゃないでしょうか。
最近注目度が上がり始めたものでいうと、PDRN(ポリデオキシヌクレオチド/サケの精子に含まれる幹細胞を培養して抽出した細胞活性因子)も挙げられますが、こういうものは、知名度を上げることにお金をたくさんかかけられる企業によって広まっているパターンがほとんどです。
コスメデコルテのリポソームなんてまさにそうですよね。お金があるプレイヤーは、“この成分がすごい”と一気に広めてそのカテゴリーを独占できるので、大きく儲けることが可能です。
リポソームはほぼほぼKOSEの独占販売です。一方、ビタミンCのように検索ボリュームがあるものを主体にした化粧品であれば、マーケティング予算がなくても参戦は可能ですが、ビタミンCのシェアを全部とることはできません。
つまり、質問の答えとしては、“お金をかけて成分そのものの認知すら自分たちで作っていく”か、“美とのコネクションがあって検索ボリュームが大きいもののシェアを取りにいく”ことで、売れる成分を扱えるということになります。
Q5「成分ドリブンで作った商品のプロモーション戦略は?」
石井:基本的には、その成分にどんな効果・効能が期待できるのか、その成分がどれくらい入っているのかを訴求していくことになりますが、商品発売時や発売後に訴求するだけでなく、発売の手前に、成分の認知度を上げるためのアクションをとれることが一番の理想です。たとえば、エクソソームの化粧品を4月に発売したいなら、2月・3月にはその化粧品の主成分のティザーを展開して知名度を上げるのが一番美しい手法と考えられます。
具体的には、成分インフルエンサーと組んで発信するといいでしょう。さらに、発売時にはマイクロインフルエンサーと組んでプロモーションを展開していくことが理想です。
成分ドリブンの化粧品のプロモーションは、いかにUGCをつくっていくかにかかっていると思います。要は口コミ施策ですね。一般の方々(インフルエンサーたち)がその成分のことを積極的に語っている状態を作り出すことが非常に大切です。
Q6「D2C向け、モール向け、オフライン向けの成分に違いはありますか?」
石井:結論としては、あると思っています。店舗で売れる価格帯、モールで売れる価格帯、自社のECで売れる価格帯が異なりますから。消費者のニーズとしては、“どこで買いたい”ということはないですが、価格と検索ボリュームの観点で調べたら違いが明確です。
たとえばAmazonで検索する人は、検索窓に“ビタミンC 美容液”と打って表示されたものを上から順にクリックするのがパターンで、見たことも聞いたこともない成分を検索することはありません。
一方、D2Cは、FacebookやYouTubeで広告を打って自社サイトに誘導してからコンバージョンすればいいので、有名な成分を入れておく必要はありません。むしろ、目新しい成分のほうがクリックされる可能性が高いといえます。さらに、価格帯としてはAmazonより数千円高く設定されていることが多いです。
オフラインに関してはどっちのタイプも売れる可能性がありますが、売り場面積が限られているから、“ビタミンCの商品は既にたくさん扱っているから新規で扱うのは難しい”とかもあり得ますよね。
総括すると、新しいものでチャレンジしたいならD2C、メジャーな成分ならモールで、オフラインならどっちでもいける可能性があるものの、いろんな商品が並んだ棚のなかから選んでもらうことが難しい場合もあるといった感じです。
Q7「今、注目している成分は?」
石井:個人的には、美容医療の領域からの転用は今後も増えていくと思います。先程お話したPDRNを含有した商品は来春には発売されると思いますし、問い合わせいただくことも増えると予想しています。ピーリング系だとBHA(サリチル酸)の人気も高まりそうだと思っています。これまではAHA(グリコール酸・乳液・クエン酸など)、PHA(グルコノラクトン・ラクトビオン酸など)が主流でしたけど、肌表面の角質ケアに特化したAHA、PHAとは違って、古い角質による毛穴の黒ずみ解消にも効果が期待できることがあって、注目度が高まりつつある成分です。
成分に関していうと、これまでは、1つの化粧品にたくさんの成分が入っているほうが好まれる傾向にありましたが、今後はless is moreになっていくと予想しています。
日本の家電が機能を追加してごてごてしていくなかで、Appleとかが機能を絞って収れんさせていった結果、後者のほうが売れている例もありますし。化粧品に関しても、成分の数より質にこだわることが大事になってくるんじゃないでしょうか。
Q8「最近は、化粧品を専属としない他業界からの参入が多いと聞きますが、どういった業界からの参入が多いですか?」
石井:ここからは、セミナー参加者様からの質問にこの場で回答していきますが、まずは、“どういった業界から化粧品業界に新規参入するケースが多いのか”といったご質問をいただいております。これに関しては、私の感覚ですが、広告マーケティング業界は多い気がします。まさに私たちもそうですが、他社様の支援を生業としていたものの、ノウハウが蓄積されていくこともあって、自分たちも参戦したいと考えるようになるパターンです。
もう1つのパターンとしては、利益率が低い業界からの参入もあります。建設業界や機械系の下請けがジリ貧になって、化粧品業界への参入することで利益を考えるようになるという流れですね。あとは、サプリメント健康食品の通販会社が化粧品に手を広げるのはもはや一般的ですね。
Q9「投資効果のイメージをご教示いただきたいです」
石井:事業のスパンをどのくらいと考えているかによっても違ってきますが、我々のケースでいうと、発売して1年で利益率20%を目標に掲げ、実際に達成してきています。ただし、20%というのは実際のところ相当レベルが高いです。ちなみに、我々は最初、小売での発売で5,000~6,000店舗でスタートしていて、最初に用意したロットが8万~10万個でした。
化粧品の上場企業は粗利が6~7割、通販専売の粗利が8~9割とされていますが、たとえばECで単価800円のものを 3,000個~5,000個売るために、広告に500万円かけてまったく売れなかった場合、900万円程度の赤字なので、初期投資がめちゃくちゃ重たいビジネスモデルというわけではないですよね。
参入障壁は低くて、失敗したときの痛手はそこまでじゃないのに、うまくいったときのリターンはでかい。だから我々も新規参入したわけですが、いっぽうで、そんなうまい話ばかりじゃないといえるのは、“新規参入しやすい≒一回シェアをとっても盤石ではなくて常に競争しなければならない”ということです。
マーケティングに関しても商品開発に関しても、常にブラッシュアップし続けることが不可欠です。オフラインの場合、棚に置かれてしまえばそれなりの地位は築けるとは思いますが、それでも、盤石とまではいえません。
Q10「商品開発、成分広告、商品広告にかける費用の割合を教えてください」
石井:これもビジネスによりけりですね。D2Cで販売している会社だと売値が高いので、商品開発というか原価は上代に対して10~20%だと考えられますが、お店に置いているわけじゃなくて自分のサイトに自分で引っ張ってくる必要があるから、CPA(Cost Per Action/Acquisition 日本語では顧客獲得単価)、CPO(Cost Per Order こちらも同様に顧客獲得単価)も考えて設定することが大切です。あくまで一般論ですが、上場している企業でも、原価率10%で広告は75~80%程度と考えられます。
一方、ロート製薬や花王などのオルファ院チャネルで販売している企業の場合、原価率は40~45%程度と考えられます。マツモトキヨシだと、自分で集客しなくても顧客が棚の前にいるわけですからね。販管費は40%、仕上がりの利益率は20%あれば相当いいほうだと考えられます。商品広告における費用はなんともいえないところがありますが、真剣に検討されている企業様はぜひ直接ご相談ください。
また、今後も月に1、2回のペースでオンラインセミナーを企画していますので、“こんなテーマで話してほしい”などのご意見がありましたらいつでもお気軽に弊社サイトからご連絡していただければ幸いです。
1時間ほどのセミナーを前編・後編で記事にさせていただきました。ベイコスメティックスでは、今後もオンライン、オフラインのセミナーを開催してまいります。
“こんなテーマのセミナーが聞きたい” ”事例について聞いてみたい” ”気軽にベイコスメティックスメンバーに相談したい” ”記事の内容についてもっと深く聞きたい” など、気になったことがありましたら以下リンク先よりお気軽にお問合せください!
サービス紹介